GOLD FISH
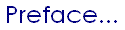
金魚は日本が北海道に生息しているヒブナを品種改良して生まれた魚です。金魚の飼育の始まりは江戸時代です。
当時は「金魚うり」と呼ばれる金魚屋がたるに金魚(当時は和金)を入れて「金魚や〜。」といいながら、街中を歩いてまわっていました。
ここでは色々な金魚について詳しく解説しています。金魚は夜店などでよく見かけるので非常に親しみやすい魚であり、
一方で非常に弱い魚でもあります。しかし正しく上手に飼えば熱帯魚よりも簡単に飼うことができます。
<ワンポイントアドバイス>金魚は金魚鉢で飼わないこと!(水槽設備が必要)

 和金(三尾)
和金(三尾)
和金の中でも特に重宝されるのがこの三尾といわれるタイプです。餌金に混じることがありますが、その場合は、たいていハネモノ(問屋で飼育用からよけられたもの)で尾びれが曲がっていたりするものなので良いものを育てようと思うならば、はじめから「三尾和金」の札がついているものを購入しましょう。ただしまれに選別ミスで餌金の中にいい個体がいることもあります。
写真・右;尾びれ先端に白が入るタイプ。左;真っ赤なタイプ。
 コメット
コメット
吹流し尾を持つアメリカ・米国ワシントン水産委員会の池で作出(というかリュウキンの突然変異がたまたま発見された)された金魚。体色には和金と同じようなバリエーションを持つものが多い。飼育の際は長い尾びれを傷つけないよう、派手なレイアウトは避ける。類似種にシュブンキン(朱文金)と呼ばれるものがいるが、こちらは三色出目金×和金での作出といわれている。吹き流し尾を持つ金魚はコメットとシュブンキン以外にもサバオという流金の体系に吹き流し尾がついた珍しい金魚が存在する。
 ワキン(更紗)
ワキン(更紗)
赤と白が混じっている体色を更紗という。上から見て左右対称に配色があるものが珍重される。飼育は普通のワキンと同様でよい。大きく育った個体は圧巻。ポピュラー(一般)品種ながらもコンテストなどでもよく出される。
 朱文金(透明鱗)
朱文金(透明鱗)
同じく透明鱗タイプ(桜タイプ)の朱文金。飼育注意点は透明鱗ワキンに準ずる。ただ、尾びれが吹流し尾のため、水槽内はすっきりと収め、尾びれに傷がつかないよう注意が必要。
 和金(フナ尾)
和金(フナ尾)
一般的には「えさ金」として売られていますが、その愛嬌のある顔は飼育する要素を十分に持っていると思います。体色のバリエーションも多々あるので気に入ったものを選びましょう。姉金と呼ばれるものは、和金のMサイズレベルの個体のことでこちらも主に餌用として入荷する。
![]()
ホームへ戻る。
 |


 和金(フナ尾)
和金(フナ尾)