 珍カラとは?
Basic course of rare characin.What is "CHINKARA"?
珍カラとは?
Basic course of rare characin.What is "CHINKARA"?
「珍カラって何?」という方、珍カラを飼ってみようと考えている方、ビギナーの方を少しでもサポートできたらと考え、このページを作成しました。全てのコンテンツの「Introduction」として、ぜひ読んでみて下さいね。
あなたも面白くて楽しい珍カラの世界へ入ってみませんか?
 珍カラという言葉
珍カラという言葉
「珍カラ」とは「珍しいカラシン」の略語です。コリドラスをやっている方ならご存知かと思われる「珍コリ(=珍しいコリドラスのこと)」と同じイメージです。「珍〜」という略し方は、今では「珍オトシン(=珍しいオトシンクルス)」なんて言葉もあるくらいアクアリウムの世界でよく使われるようになりました。
 珍カラとはどんな魚を指すのか?
珍カラとはどんな魚を指すのか?
珍カラとはどんな魚を指すのでしょうか?
具体的に「この種類からこの種類までが珍カラだ」という明確な定義はなく、カラシンの仲間で(特に小型カラシンの)入手困難な種類のカラシンを指すようです。また珍カラの中でも学名不詳(学名が決定していない、学術論文に未掲載である)の種類を便宜上「謎カラ(=謎のカラシン)」と呼ぶこともあります。ここで注意したいのは単に学名不詳なだけでは珍カラとは言えない点です。
例えばテトラ・オーロ
がそれに該当します。テトラ・オーロというカラシンは学名不詳とされていますが、数多く輸入・流通しており珍カラとはいえません。つまり珍カラとは、「学名が明確or不明確に関わらず、輸入数(採集数)や流通数が著しく少ないカラシン」という定義を満たすカラシンを指すと考えていただければと思います。


(上)赤目金線テトラと総称される個体群
上の写真のように赤目で体側に金線が入る個体は総称して「赤目金線テトラ」と呼ばれるカラシンは数種存在することが知られていますが、ほとんどがカージナルテトラやグリーンネオンなど他種に混じって輸入されます。このようなカラシンは単独での輸入が少なく他種の混じりとして輸入されることが多いため、珍カラと言えます。


また上左の写真のような金色(ないしは銀色)に輝く"プラチナ個体"や、上右の写真のようなメラニン色素の欠落による"白変個体"などの「突然変異」の個体は出現数が極端に少なく、入手も非常に困難であるため先に紹介した「赤目金線テトラ」以上に珍カラと言えます。
| 珍カラとは?・・・・・「学名の有無に関わらず、輸入数や流通数が著しく少ないカラシン」 |
|
 珍カラのコレクションと混泳
珍カラのコレクションと混泳
珍カラを色々とコレクションする場合はできるだけカラシン以外の他魚とは一緒に入れないほうが無難です。混じり抜きで入手した珍カラはどんな性格か、最大何cmまで成長するのかなど詳細が不明な場合も多々ありますので、思いの外デリケートな性格で他魚にイジメられてしまったり、逆に他魚がイジメられる可能性も否めません。中にはスケールイーターと呼ばれる他種のウロコを好物とするカラシンも存在します。このようなトラブルを避けるためにもまた少しでも珍カラを多く収納するためにも珍カラオンリーの水槽をつくるのがおすすめです。
カラシンの飼育についてさらに詳しく>カラシンの飼育法
 注意すべき珍カラ
注意すべき珍カラ
 |
グラス系の珍カラ(例えば左写真のネグログラステトラ)は総じて水質に敏感で、餌の与えすぎなどにより水質が悪化すると、体の中が白く濁る病気にかかりやすいので、導入時の水合わせは慎重に行い、餌の量に関わらず定期的な換水を実施し、水質に気を遣うよう心掛けることをおすすめします。 |
ショップに入荷する珍カラの中には同じ種類であるにもかかわらずそれらが複数の名前で流通することがよくあります。 |
例えば左の写真のカラシンは「レッドベリーテトラ」「ピンキーテトラ」「ヘミグラムス・カエルレウス」などの名前で販売されますが全て同種とされています。これは1種類の魚にシッパー、問屋、ショップの3者がそれぞれで違った名前を付けているためと考えられます。「違う名前で購入したのに、成長してみたら以前に買ったカラシンと同じ種類だった。」なんてこともよくある話です。よって購入時には見極めが必要です。 |
 珍カラを見つけに行こう!
珍カラを見つけに行こう!
珍カラを安値でゲットするには、南米やアフリカから輸入されてくる比較的入手容易なワイルドカラシンの袋の中に現地スタッフ及び問屋スタッフの目を逃れて、数匹混ざっている別種を入手する(つまり本来、袋の中にいる魚とは違う種類。)混じり抜きという方法があります。まずはこの方法で珍カラを入手してみましょう。
混じり抜きについてさらに詳しく>混じり抜き方法
 珍カラは地味??
珍カラは地味??
珍カラというのは地味である。という第一印象を抱かれる方が多いと思いますが、一見地味に思える種でもじっくり育てていくと大変美しい発色を見せる種類も沢山います。
 | 例えばカージナルテトラやグリーンネオンなどによく混じっている黒点系のカラシン(左写真)は珍カラの中でも地味だという印象を持っている方が多いと思いますがこのようなカラシンもベストな水で飼育してやれば十分映えるカラシンに変身します。珍カラの楽しみというのはただ混じり抜きをしコレクションしていくだけでなく、個々の魚の性質を自分なりに研究し、それぞれの発色をじっくり引き上げるという楽しみ方もあるのではないかと思います。 |
当サイトを通して珍カラに少しでも親しみを持っていただければ幸いです。
そしてカラシニストがさらに増える事を願ってやみません。
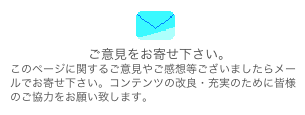
 |

