Cure and treatment
薬剤師が教える
カラシンにおける病気の治療法
 始めに・・・
始めに・・・
カラシンにおける疾患の治療は薬物治療が基本となる。しかし魚体のサイズに比例して免疫は弱く、その治療はなかなか難しいことが多い。従ってできる限りの早期発見・早期治療が重要であり、同時に未感染魚への感染を防ぐことが1つのポイントである。ここではカラシンやその他小型魚が感染しやすい病気の症状と治療法を薬剤師である私の経験とプロショップスタッフのご協力の下、掲載したので参考にして欲しい。
・注)病名が不明な場合は、順にクリックして当てはまる症状の病気のページをご覧下さい。
・注)ここに記載した治療法は実際に管理人がプロショップ様のご意見を取り入れたものや実際に試したものです。
・注)些細な治療環境等で結果が変わることがありますので予めご承知置き下さい。ご不明点は治療を施す前にコミュニティにてご相談下さい。
 病気の治療上の注意
病気の治療上の注意
カラシンやその他の観賞魚が病気に罹った時に用いる機会が多いのは市販の各種魚病薬である。しかしどの魚病薬も万能ではないことは予め理解しておく必要がある。魚病薬は一般にいかなるときも規定量の添加を心掛けたい。ここで魚病薬を規定量未満の濃度で使用してしまうと病原となる細菌・ウイルスが魚病薬に対して耐性を持つようになるため次回の治療時から本来期待できる効果が見られなくなることがあるので注意が必要だ。(薬剤耐性菌の出現。)また一般に魚病薬に弱いとされているコリドラスなどナマズ類についても、添付文書に別途ナマズ類への規定量や使用上の注意喚起が記載されていない限りは他魚同様に定められた規定量通りの添加を行うことが理想である。ちなみにカラシンではナマズ類のようなケースバイケースな例外はなく、どの種類も規定量の添加をみなして全く問題はない。
とにかく基本は「定められた規定量」を守って添加することが早期完治への近道である。
規定量を守ることの他に注意すべきはそれぞれの病態に適した各種魚病薬の選択である。例えば、細菌性感染症の魚に抗ウイルス薬や抗寄生虫薬を投与しても全く効果はない。魚病薬はそれぞれの適応疾患にのみ効果を発揮する。魚が病気に罹ったらまずはどのような疾患なのかを正確に診断する必要がある。
 各種魚病薬の性質
各種魚病薬の性質
魚病薬の中で使用に際して注意が必要なものを挙げる。治療の際は魚体の衰弱具合を勘案して適量換水を行い、できるだけ飼育水がクリーンな状態で薬浴したほうが効果的である。またマラカイトグリーン水溶液やエルバージュなど薬によっては光を触媒として分解してしまうものがあるので、治療は暗い場所で行うのが良いだろう。
・エルバージュ
ニフルスチレン酸ナトリウムを主成分としている。飼育水は黄色に染まる。細菌性感染症に用いる。光で分解されやすいため暗めの環境で薬浴する。重症時の魚に対しては塩と供用して吸収力を高めることもある。
・観賞魚用パラザンD
オキソリン酸が主成分で、pH値が高く、アルカリ性(pH11.0前後)を示す。エルバージュ同様、細菌性感染症に用いるが、光で分解されにくいため扱いやすい。ただし重症時にはエルバージュのほうが効果的。
・グリーンFゴールド リキッド(液体の薬品)
パラザンD同様にオキソリン酸を主成分としているが、黄色4号(着色料)が加えられており飼育水は黄色に染まる。光分解を受けにくい。pHは11.0前後を示す。
・グリーンFゴールド 顆粒(要時溶解の粉末の薬品)
同名のグリーンFゴールド リキッドとは異なり、ニトロフラゾンとスルファメラジンを主成分としている。このうちニトロフラゾンが光分解を受けやすいため暗めの環境で薬浴する。飼育水を適量取り溶解してから魚のいる水槽に加える。飼育水は本剤の溶解で黄色に染まる。 |
 塩浴について
塩浴について
本ページ中で登場する塩浴の詳しい方法についてはコチラをご参照下さい。
 白点病
白点病
治療のポイント:水温を30度までゆっくりとあげ、あら塩を投入するか、水温を上げた上、マラカイトグリーン水溶液で薬浴する。
原因菌:繊毛虫の1種であるイクチオフィチリウス(Ichthyophthirius multifiliis)が魚体に表面に寄生することによって発症する病気である。白点1つが病原体1匹である。
原因菌の特徴:魚体表面に吸着するようにして魚の体力を奪う。魚体寄生時には肉眼で確認可能。本病原菌は高水温に弱く、水温28〜30度程度で繁殖を停止する。感染率は高い。普段は土中(砂利中)や水中で生活するため、魚体に寄生していない場合は発見できない。
発生域:淡水、海水。(但し海水魚における本病はまったく原因が異なる別ものである。)普段は(魚体寄生時以外は)底床中や水中に潜んでいる。
発症のきっかけ:本病における発症のきっかけにはいくつかが考えられる。次にそれを列挙した。
1.高感染率時
水温の急変、低水温状態時、入荷直後(注2.)(低抵抗力時)
2.日常感染時
新たな魚の投入(=原因菌の持ち込み)、傷を負った魚が存在する時
3.感染方法
おおまかには、イクチオフィチリウスが魚体表面に直接付着・寄生し、発症、感染する。
 |
左図はイクチオフィチリウスの生活環を示している。
繊毛虫の1種であるイクチオフィチリウスは水中で様々な形態をとる。魚体に寄生するとホロントとなり、ホロントが成虫になると魚体を離れ、シスト(被嚢)となる。シストは水中や底床で増殖・分裂を繰り返し、やがて遊走子を放出する。この遊走子が再び魚体に寄生する。このとき寄生できなかった遊走子は約2日で死滅する。次に示す魚病薬はシストの時期と遊走子として漂う時期(魚体に寄生する前)に効果を示す。イクチオフィチリウスのこのサイクルは1週間弱で一周する。すなわちホロントが魚体から離れ、シストまたは遊走子に分化し、魚病薬でそれらが殺菌されて始めて治療できたといえる。 |
症状:初期症状として体を岩などにこすりつけるような行動を見せる。その後、体及び尾びれ各所に白い1ミリから2ミリほどの白い点が付着。末期にはエサ食いが悪くなり、呼吸器官の中枢であるエラが犯され、魚が死亡する。
初期…ヒレに白点/中期…ヒレ及び体側に白点/末期…ヒレ、体側に多量の白点。この時期にはエラが犯され、呼吸困難を伴う。
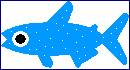 末期にはヒレ及び体側に大量の白点。
末期にはヒレ及び体側に大量の白点。
治療法:水温を30度まで少しずつ上げ、あら塩を60センチ水槽でスプーン1杯投入。初期段階の場合、これだけで数日後完治することもある。
これでも回復、完治なき場合は市販の白点病用の魚病薬(マラカイトグリーン水溶液が最も効果的である。グリーンF水溶液は場合によっては効果が少ない。)に病気の魚を規定期間、暗めの場所で薬浴。一般に白点病には飼育水が緑色に染色される魚病薬が効果を示す。ただし、末期の場合は甲斐なく死亡するケースが多い。早期発見と初期段階での治療が完治のカギ。慣れれば病気の進行状況もわかり、初期段階での治療は朝飯前の病気なので感染してもあわてず落ち着いて対処しよう。
類似病:白点病より細かい白点が各所に付着する別の病気も知られ、一般にコショウ病(ベルモット症)と呼ばれている。治療法は白点病に準ずるが、こちらは初期でも高水温だけでは完治しにくい。
(注1.)約2日間、魚体に寄生できないとイクチオフィチリウス(=遊走子の時期)は死滅する。
(注2.)例外的に、入荷・導入直後に発症する本病は一度治る方向に向かえば再び悪化することは少ない。
 水カビ病
水カビ病
治療のポイント:マラカイトグリーン水溶液で薬浴する。塩浴と併用が効果的。
原因菌:Achlya属、Saprolegnia属、Aphanomyces属のミズカビが魚体に付着することによる。口に付いた場合はマウスファンガス症や口腐れ病とも呼ばれる。
原因菌の特徴:主に魚体の傷に付着することにより感染する。従って、水中にミズカビが存在しても、魚に傷がなければ感染することはない。
発生域:淡水の場合がほとんど。
発症のきっかけ:魚体の傷にミズカビが付着することにより感染する。網で魚を掬った後などは魚体に傷が付いてしまうことが多いので注意を要する。
症状:魚体表面、口、各ヒレ、エラ部などに白い綿のようなもの=ミズカビが付着する。
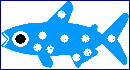 体表の各部位にミズカビが付着する。口に付いた場合は口腐病とも呼ばれる。
体表の各部位にミズカビが付着する。口に付いた場合は口腐病とも呼ばれる。
治療法:早期発見早期治療で本病は比較的治療が楽である。マラカイトグリーン水溶液やグリーンFなど飼育水が緑色に染色される魚病薬を規定量添加した飼育水で薬浴する。薬浴は薬品の光による分解を防ぐため暗めの場所で行う。また白点病の際と同量のあら塩による塩浴と併用すると効果的。
 カラムナリス症
カラムナリス症
治療のポイント:早期発見早期治療がカギ。感染した魚の死亡率は高いため、治療より、他魚への感染を防ぐ。
原因菌:多くはフレキバクターカラムナリス(Flexibacter columnaris)で知られるフラウォバクテリウム菌(他、サプロレギニア、アファノマイセス)
原因菌の特徴:症状はケースバイケースであり、感染率も高い、恐れられている病気の1つ。人間の皮膚に付着することもあるが、人間に対しては感染・発症はしない。
発生域:淡水
発症のきっかけ:本病における発症原因は次の中のいずれかであることが多い。
1.高感染率時
新たな魚の投入時、入荷直後(免疫低下時)
2.日常感染時
新たな魚の投入(=原因菌の持ち込み)、傷を負った魚が存在する時、エラ器官の欠陥時
3.感染方法
A、魚体表面に直接付着し、感染する。
B、エラに感染し、エラ病などを併発。
C、体内に潜伏。
症状:エサ食い悪化、魚体表面より粘液の過剰分泌のよる飼育水の悪臭、魚体の部分的な色彩の薄れ、痙攣、魚体のこすりつけなど。
治療法:塩水浴、過マンガン酸カリウム水溶液での薬浴、ホルマリン浴が効果的。市販の飼育水が黄色に染まる細菌性感染症治療薬(エルバージュ、グリーンFゴールドなど)の規定量添加も効果的。発生水槽内のアクセサリー、水草、砂利は原因細菌が生息している恐れがあるため、すべて処分。完治は難しく、死亡率、感染率ともに非常に高い。そのため治療より他魚への感染を防いだほうがいい。
類似病:症状によってはエロモナス症との区別が難しいが、治療法はいずれの場合もほぼ同じである。
備考:フレキバクター・カラムナリスは現在ではフレキバクター(Flexibacter)属ではないとされているが、ここでは便宜上、広く知られている「フレキバクター」の記述を用いた。
尾ぐされ病、エラ病もフレキバクター・カラムナリスによるものである。
 エロモナス症
エロモナス症
治療のポイント:飼育水が黄色になる魚病薬で薬浴。同時に感染魚のいた水槽ごと同薬で規定量規定期間薬浴。
原因菌:運動性エロモナス類=Aeromonas hydrophila、非定型(非運動性)エロモナス=Aeromonas salmooicida
ほかビブリオ科の細菌Pseudomonas fluorescensによって起こるものもエロモナス症と呼んでいる。
病気のタイプ:非定型エロモナス症、運動性エロモナス症
原因菌の特徴:適切に管理された環境では発症率は高くはない。エロモナス菌は水中常在菌で常に飼育水内に存在し、水質悪化など一定条件が揃うと病原性を発揮する。普段は有害な菌ではない。感染した魚の死亡率は非常に高い。感染率にはエロモナス菌やビブリオ菌の型により差がある。
発生域:本病は通常「穴あき病」と呼ばれる非定型エロモナス症、運動性エロモナス症などに区分され、発生水域に差がある。
・非定型エロモナス症(=穴あき病)=淡水
・運動性エロモナス症(=ポップアイ、松カサ病、注;いずれも後述の腹部膨張を伴うことが多い、腹部膨張、赤斑(血がにじんだよう)、口が開いたまま)=淡水、汽水
原因:
1.高感染率時
水質悪化時、環境悪化時、老廃物蓄積時、入荷直後(免疫低下時)
2.日常感染時
きちんと管理していれば日常発生することはない。飼育水が古い場合に発症する例が多い。
3.感染方法
エラ部もしくは傷口から進入し感染。
症状:眼球突出(ポップアイ)(写真矢印2.、3.)、鱗の逆立ち(逆鱗症状・松カサ病)、エサ食いが悪くなる、腹部膨張、赤斑(血がにじんだよう)、呼吸が非常に速い(過呼吸)(写真矢印1.)など。症状はさまざま。初期症状としては共通して腹部膨張が見られる場合が多い。
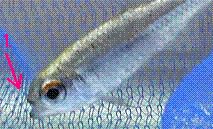 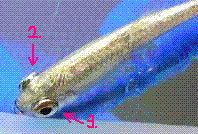  | 過呼吸症状(矢印1.)や、眼球突出(矢印2.及び3.)はエロモナス症の典型的症状。
4.は腹部膨張及び眼球突出を上から観察したもの。よく見ると逆鱗症状も観察される。 |
治療法:一般に、エルバージュなど飼育水が黄色に染まる魚病薬で規定量の薬浴を行うが、本病を発見した時(即ち肉眼で確認できた地点で)にはすでに重症になっていることが多く、完治は困難を極める。そのため、他魚への感染を防ぐのに力を注いだほうがよい。まずは感染魚の隔離。つぎに感染魚が見つかった水槽の飼育水にエルバージュを規定量投入し(常在菌であるため、飼育水内を浮遊している場合は問題ないが、他に感染魚が居ないように見えて魚体内に潜伏していることが殆ど。)、魚、アクセサリー、砂利ごと規定期間薬浴。水草は完全な洗浄が困難であるため処分する。また感染が見つかった水槽の環境を根本的に見直す必要がある。(リセットが望ましい。)とくに水槽の水に問題がないか(水質悪化など)など調べる。
備考:エロモナス菌はいずれも常在菌(常に水中に生息している)であり、抵抗力の低下した魚体や水質の悪化などがない場合は水中を浮遊している。しかしひとたび水質が悪化したりすると魚体に侵入し発症する。従って日ごろの細かな管理が本病を防ぐ最大の方法といえる。
類似病:非定型エロモナス症(=穴あき病)(淡水で発生。症状は上記に準ずる。本病も上記同様に治療は難しいが、原因菌であるAeromonas salmooicidaは低水温を好むため、水温を普段よりも上げて上記同様の治療および処置を行う。金魚、コイ、フナなどが罹りやすい。とくにコイに発症した場合にはコイヘルペスと呼ばれる。)
 カラシン病(ネオン病)
カラシン病(ネオン病)
治療のポイント:早期発見し、エルバージュなどのニフルスチレン酸ナトリウム含有の薬品か、パラザンなどのオキソリン酸含有の薬品で薬浴。ショップが、トリートメントをする際に使用しなかった薬を選んだほうがよい。
原因菌:フレキバクター・カラムナリス(Flexibacter columnaris)によるものとミコバクテリウム属(Micobacterium)によるものがある。
発生域:淡水
発症のきっかけ:本病は発症原因が明らかでなく、水質悪化時、古い飼育水による長期飼育や新しい魚導入時にかかりやすいように思える。
新規魚購入時は発色のよくない個体は避けるよう心がけ、飼育水槽も定期的な水換えを怠らないようにすることが予防としてよいだろう。
疾患詳細及び主な症状:カラシンの中でも蛍光色の模様を持つ種類(ネオン、カージナル、グローライト、ブラックネオン、グリーンネオンなど。)が罹りやすい病気(実際、ショップでネオン病に感染したカージナルと同じ販売水槽に蛍光ラインのない混じりが数匹いたが、この混じりは購入してきてもネオン病は発病しなかった。)で、症状、死亡率、治療難易度から見て最も恐ろしい病気と言っても過言ではないだろう。本病はその症状も様々で、中には本病と気づきにくい症状もあるため発見時には手遅れとなっていることが多い。代表的な症状を次に列挙する。
1、体内部が充血したように赤くなる。(フレキバクター・カラムナリスの代表的な症状である。)
2、目が飛び出る。(この症状を「ポップアイ」という。ミコバクテリウム属による場合に多い)
3、口が大きく開いたまま泳ぐ。
4、体内部が白く濁り、だんだん広がっていく。
5、狂ったような泳ぎ方をする。
6、何の症状なく次々と死亡する。(体内に異常があり、表面には症状がでないと考えられる。)
7、ネオンテトラのように体側に蛍光色のラインを持つ種類の場合はラインの発色が劣化・薄化したように見える。
などなど。
フレキバクター・カラムナリスによるネオン病の場合、感染力が強く次々に死亡し、数日で全滅するが、ミコバクテリウム属によるネオン病の場合、感染力はそう強くなく慢性的なもので、ポツポツと時間をかけて死んでいく。
治療法:いずれも治療法としては確立されたものがなく、大抵は飼育水が黄色に染色される魚病薬、例えばパラザンやエルバージュ、グリーンFゴールドを用いて水温を23〜26度ほどに下げた上で薬浴を行う。これらの魚病薬の吸収性を高めるために、魚のエラを開かせる効能を持つ、荒塩(量は白点病に同じ)を併用してもよい。ただしこうした方法でもすでに罹っている個体の完治は困難で、投薬後、感染魚(症状は出ていないが病気が潜伏していた個体も含む)が相次いで死亡することが多い。つまりパラザンやエルバージュの投入は未感染の魚への感染を防ぎ、水槽全体を消毒する意味での投入だと思ったほうがよい。この病気の原因菌の1つであるフレキバクター・カラムナリス菌はエロモナス菌同様、水中常在菌(常に水中に存在する。)で普段は悪さを働くことはないが、飼育水が古くなってくると魚に寄生・感染する。よって予防には定期的な水替えを行い、常に水質をよく保つことが重要だろう。
ショップでは本病の発症を防ぐため、入荷直後の魚に魚病薬でトリートメントを施していることがあり、その際に生き残った細菌が使用した魚病薬に対し抵抗力を持っている(薬剤耐性菌に変化している)ことが多く、病気再発時には同じ魚病薬では本来の効果が見られないことがあるので注意しよう。
備考:フレキバクター・カラムナリスは現在ではフレキバクター(Flexibacter)属ではないとされているが、ここでは便宜上、広く知られている「フレキバクター」の記述を用いた。
尾ぐされ病、エラ病もフレキバクター・カラムナリスによるものである。
 部分的な黒化現象
部分的な黒化現象
治療のポイント:半分強の換水を週おきに行う。
原因:はっきりしたことは不明であるが、メラニン色素細胞の異常によるものと考えられる。
発生域:淡水
発症のきっかけ:病原菌によるものではないと思われる。飼育水の汚れがひどいときなど環境の悪化が引き金となるようだ。
疾患詳細及び主な症状:体表の一部分または全体が通常よりも暗色化(黒化)する。ひどい場合は各ヒレにも及ぶ。初期は魚体自体は比較的元気で、餌食いも悪くなることは少ない。
治療法:明確な治療法は確立していないようだが、私の経験では、症状を確認した地点で、2分の1強の換水を行い、これを症状が改善するまで週おきに行うと症状の緩和がほとんどの場合確認できた。ただし進行すると泳ぎがぎこちなくなりやがて死亡する。
備考:病原菌によるものではなく、色素細胞(メラニン色素)の後天的な異常が原因と思われる。
 部分的な体内白濁
部分的な体内白濁
原因:多くは骨に並行して分布している筋肉組織の異常によるものとされる。その他、pHショックなどにより一時的に体内が白濁する場合、カラムナリス菌やエロモナス菌など病原菌による場合もある。
発生域:淡水
発症のきっかけ:カラムナリス菌やエロモナス菌などの病原菌による場合もあるが、多くは飼育環境の悪化(飼育水の水質悪化など)が要因となっていると思われる。
疾患詳細及び主な症状:魚体の一部分、小型カラシンでは特に背中側の体内が白濁したように見える。初期は魚自体は元気であるが、白濁面積の拡大とともに弱っていき、ひどい場合は死に至ることもある。
 グラステトラに発症した運動性エロモナス症に伴う体内白濁。
グラステトラに発症した運動性エロモナス症に伴う体内白濁。
治療法:pHショックによるものの場合、数日で症状は自然に改善されることが多い。筋肉組織の異常や病原菌による場合、飼育水の2分の1程度の換水など飼育環境改善、エルバージュやパラザンなど飼育水が黄色に染まる魚病薬による規定量薬浴により徐々に改善していくことがあるが、確実な改善方法は今のところないようだ。
備考:背コケ病とも呼ばれる。
 グリーンネオンなどに好発する線虫の寄生(ここでは便宜上カラシン線虫と呼称する)
グリーンネオンなどに好発する線虫の寄生(ここでは便宜上カラシン線虫と呼称する)
概要:グリーンネオンなどによく見られる、体表、各ヒレ、エラ部、目の周囲などに白いひも状の線虫が寄生する疾患。新規にグリーンネオンなどの小型カラシンを導入した後に見られることが多い。
原因:新規導入後によく見られる。原因となる白いひも状の線虫に似たものはコリドラスでもよく見られるがコリドラスに寄生する線虫(以下コリドラス線虫)はダクチロギルス(Dactylogyrus)属またはギロダクチルス(Gyrodactylus)属であるとされるところ、コリドラス線虫がカラシンに感染することはほぼなく、カラシン線虫はそれらとは別種・別起因と考えられ、種類など詳細は定かではない。
発生域:淡水
症状:体表、各ヒレ、エラ部、目の周囲などに白いひも状の線虫が寄生する。初期では肉眼で確認できないこともある。
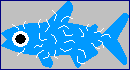 体表に白いひも状の線虫が寄生する。
体表に白いひも状の線虫が寄生する。
治療法:本症にはムシクリアやブラジプロなど一般的な寄生虫駆除薬は無効であり、外科的処置を要する。寄生された魚を水を薄く張ったシャーレ上か濡らしたガーゼ上に置き、先の細いピンセットを用いて、すばやく寄生虫を除去した上、処置部位からの二次感染防止のためエルバージュ、パラザン、グリーンFゴールドなどの細菌性感染症薬で薬浴する。ただし寄生により衰弱が進行していた場合、これらの処置をもってしても死亡する場合がある。
 各疾患の治療チャート
各疾患の治療チャート
| 病名 |
主な原因菌 |
主な症状 |
治療薬 |
治療水温 |
治療中の給餌 |
| 白点病 |
イクチオフィチリウス |
ヒレや体側に白点 |
マラカイトグリーン水溶液、グリーンF、塩化ナトリウム、唐辛子(鷹の爪) |
高(29〜30度) |
有 |
| 水カビ病 |
Achlya属、Saprolegnia属、Aphanomyces属のミズカビ |
ヒレや体側に白綿状の水カビ |
マラカイトグリーン水溶液、グリーンF、塩化ナトリウム |
低 |
無 |
| カラムナリス症 |
フレキバクター・カラムナリス |
体色の薄化、体表粘液の過剰分泌など |
エルバージュ、パラザン、グリーンFゴールド、塩化ナトリウム |
低 |
無 |
| エロモナス症 |
各種エロモナス菌 |
眼球突出、立鱗、腹部膨張、赤斑、過呼吸など |
エルバージュ、パラザン、グリーンFゴールド |
非定型の場合のみ:高 |
無 |
| ネオン病 |
フレキバクター・カラムナリス、ミコバクテリウム属菌 |
体内白濁、体色の薄化、過呼吸、狂泳、眼球突出、充血、突然の大量死など |
エルバージュ、パラザン、グリーンFゴールド、塩化ナトリウム |
低 |
無 |
| 部分的な黒化現象 |
メラニン色素の異常 |
部分的、全体的な体表の暗色化 |
半分強の換水など飼育環境改善 |
無 |
有 |
| 部分的な体内白濁 |
筋肉組織の異常、pHショック、病原菌など |
体内の白濁 |
エルバージュ、パラザン、グリーンFゴールド |
無 |
無 |
| グリーンネオンなどに好発するひも状線虫の寄生 |
ひも状線虫の寄生 |
体表へのひも状線虫の寄生 |
ピンセットを用いできる範囲で線虫を除去した上、エルバージュ、パラザン、グリーンFゴールド |
無 |
有 |
注;治療の際は必ず各種疾患の詳細をページ上にてご確認下さい。
注;文中もしくは上記表中の「グリーンFゴールド」は特に注釈のない限り、リキッドタイプでも顆粒タイプでもよい。ただしそれぞれで遮光の必要の有無が異なるので注意する。詳しくはページ上部「各種魚病薬の性質」を参照のこと。
注;塩化ナトリウムが入手できない場合は市販の荒塩を添加。塩浴の詳細はコチラ。
注;フレキバクター・カラムナリスは現在ではフレキバクター(Flexibacter)属ではないとされているが、ここでは便宜上、広く知られている「フレキバクター」の記述を用いた。
[MENUに戻る]
ホームへ戻る。
 |
